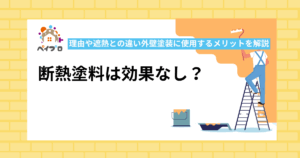「ウレタン防水って本当に長持ちするの?」「ほかの防水とどう違うの?」このような疑問を抱えていませんか?
本記事ではウレタン塗装防水の基本から、他工法との違い、メリット、デメリットまで徹底解説します。ウレタン防水を正しく知ることで、費用もリスクも抑えた施工が実現可能です。
施工前にウレタン防水の特徴を知り、失敗せず施工を行いましょう。
\ 簡単30秒! /
ウレタン塗装防水の基本を押さえよう

ウレタン塗装防水とはどんな工法で、どのような建物に使われているのでしょうか。施工トラブルを避け、最適な選択をするためには基礎知識の理解が不可欠です。
まずはその定義や使用場所、普及した背景を詳しく見ていきましょう。
ウレタン塗装防水とは何か
ウレタン塗装防水は、液体状のウレタン樹脂を塗り広げて硬化させる工法です。時間をかけて硬化させるため、つなぎ目のないシームレスな防水層を形成できます。
施工場所の形状に関係なく均一に塗ることができるのも特徴。特に複雑な形状のベランダや屋上などで、威力を発揮します。
防水層が隙間なく下地に密着するため、水の侵入を防げます。建物を、長期的に保護できます。
主な施工場所と利用シーン
ウレタン塗装防水は柔軟性と密着性から、以下の場所で多く使用されています。
- 戸建て住宅のバルコニーやベランダ
- マンションやアパートの共用廊下や屋上
- 商業ビルや倉庫の屋根部分
- 鉄骨造やRC造の陸屋根
また、既存の防水層の上に重ね塗りできる改修工事にもおすすめ。下地を剥がさず、工期を短縮できる点が大きな魅力です。
ウレタン塗装防水の普及の背景
ウレタン塗装防水が普及した背景には、いくつかの要因があります。
まず、液状の材料で施工性が高く、下地の形状を選ばない柔軟性が重宝されていること。そして材料費や人件費ともに比較的リーズナブルなので、コストパフォーマンスに優れる点も人気の理由です。
日本特有の高温多湿な気候に適した防水性能を持つことも、広く受け入れられている要因です。
ウレタン防水と他の防水工法の違いを比較

ウレタン塗装防水の特性を理解するには、他の代表的な防水工法との違いを知ることが大切です。建物や用途によって最適な工法は異なるため、比較することで失敗を防げます。
ここでは各防水法の特徴と注意点を比較して解説します。
FRP防水との違い
FRP防水は、ガラス繊維を混ぜた樹脂を塗布して固め、強固な防水層を作る工法です。ウレタンと比較すると硬くて耐久性に優れているため、屋上駐車場など車両が通る場所に適しています。
ただし、硬質であるがゆえにひび割れやすく、建物の揺れによる動きには弱い面もあります。その点、ウレタン防水は柔軟性があり揺れに追従できるため、住宅の屋根やベランダに向いています。
シート防水との違い
シート防水は、塩ビやゴム製の防水シートを接着剤などで貼り付けていく工法です。施工スピードが速く、工期短縮を図りたい場合におすすめ。しかし、下地の形状によっては施工が難しいケースもあります。
細かい凹凸や立ち上がり部分がある箇所は、ウレタン防水が向いているでしょう。
アスファルト防水との違い
アスファルト防水は、熱で溶かしたアスファルトを下地に何層にも塗り重ねていく昔ながらの工法です。非常に高い耐久性を誇りますが、施工時に火気を使用するため安全性や近隣への配慮が必要です。
また、重量があり建物への負荷も大きいです。建物への負担を減らすためにも、軽量で環境にも配慮されたウレタン塗装防水が、近年では選ばれています。
他の防水工法との違いを把握しておくと、どの防水が適切か判断できるでしょう。
\ 簡単30秒! /
ウレタン塗装防水の特徴と3つのメリット

ウレタン防水には、他の工法にはない柔軟性や軽量性、一体化など多くの利点があります。これらの特性は、建物の性能や寿命にも大きく関わってきます。
次の項目では、ウレタン防水の代表的なメリットを3つの視点から解説していきます。
複雑な形状にも対応できる柔軟性
ウレタン塗装防水の最大の特徴が、どんな形状の場所にも対応できる柔軟性です。
液体状のウレタン樹脂を塗布するため、凹凸のある下地や立ち上がりのある部分、ドレン周辺などに使用可能です。他の防水工法では施工が難しい箇所でも、確実に防水層を形成できます。
また、既存の構造物や設備をそのまま残して施工できる点もメリットです。柔軟な性質を持つため、地震や建物の揺れにも追従しやすく、ひび割れのリスクも最小限に抑えられます。
軽量で建物への負担が少ない
ウレタン塗装防水は非常に軽量なため、建物全体にかかる負担が少ない点も魅力の一つです。
特に、既存の防水層を撤去せず重ね塗りできる「カバー工法」では、施工後の重量増が建物の負担になる場合があります。ウレタン防水は非常に軽量なため、そうしたケースでも安心して使用できるのが大きな特長です。
例えば、老朽化した木造住宅のベランダや屋根でも、建物にダメージを与えず防水性を高められます。ウレタン防水の軽量性は、建物の健康寿命を延ばせます。
継ぎ目のない一体化した防水膜
ウレタン塗装防水は塗布によって硬化させるため、施工面全体が継ぎ目のない一体化した防水層となります。シームレス構造が最大の強みであり、シート防水のように継ぎ目から水が浸入するリスクが極めて低いです。
また、シームレスな膜は見た目にも美しく、仕上がりにムラが出にくい点も魅力です。雨水の侵入を防ぎ長期間防水性能を維持できるため、耐久性を重視する方におすすめです。
ウレタン塗装防水のデメリットと注意点

どれほど優れた防水でも、短所や注意すべきポイントは存在します。施工不良や劣化を防ぐためにも、ウレタン防水の弱点を把握しておくことが重要です。
以下では、寿命・施工時の注意・メンテナンスリスクについて解説します。
劣化が早く寿命は10年
ウレタン塗装防水の耐用年数は、一般的に10年程度です。FRP防水やアスファルト防水と比べるとやや短めであり、経年による劣化が早いです。
特に、直射日光や風雨にさらされる場所ではトップコートが摩耗しやすく、防水性能が徐々に低下します。そのため、10年を目安に再塗装や全面補修が必要です。
施工に時間がかかり下地処理も必要
ウレタン塗装防水は、液体を何層にもわたって塗布し乾燥させるため、施工完了までに時間がかかります。また、下地の状態が悪い場合は補修作業が必要となり、工期が延びる可能性があります。
気温や湿度が施工に大きく影響するため、梅雨や真冬などは慎重に行わなければいけません。急いで工事をしたい方には不向きな場合もあるので、事前の打ち合わせが重要です。
施工後の定期的なメンテナンスが必要
ウレタン防水は定期的なメンテナンスが不可欠です。特に、トップコートが紫外線や風雨にさらされることで徐々に劣化します。劣化を防ぐためにも、5年ごとを目安に塗り替えを行わなければいけません。
メンテナンスを怠ると、最終的には防水層が傷んでしまいます。大規模な改修が必要になるため、施工後も継続的な点検とメンテナンス計画が必要不可欠です。
\ 簡単30秒! /
ウレタン塗装防水の費用相場と見積もりのポイント

ウレタン防水の費用は条件により大きく異なり、見積もりの読み方ひとつで総額に差が出ます。コストを抑えつつ、質の高い施工を実現するには相場感と注意点を押さえることが不可欠です。
ここでは、費用の内訳や見積もりで注目すべき点を詳しく紹介します。
一般的な費用帯と要因
ウレタン塗装防水の費用は、1㎡あたりおよそ4,000円〜7,000円が相場です。密着工法であれば比較的安価に済みますが、通気緩衝工法は施工の手間や材料費が増え、単価も高くなります。
費用に影響を与える主な要因は以下の通りです。
- 施工面積
- 下地の劣化状況
- 使用する材料のグレード
- 建物の立地や作業環境(足場の有無など)
小規模なベランダ防水なら20万円前後。大規模な屋上全体を施工する場合は、100万円を超えることも珍しくありません。
追加工事や下地補修の確認

見積もり時に見落としがちなのが、追加工事の有無です。例えば、下地にひび割れや浮きなど劣化がある場合は、事前に補修を行わなければいけません。補修費用が別途見積もりとなっている場合、後から追加請求されるため注意が必要です。
また、以下の費用が見積書に含まれているかどうか、契約前に必ず確認しておきましょう。
- 排水口やドレンまわりの処理
- 既存防水層の撤去作業
- 廃材の運搬・処分費用
上記はウレタン防水工事で意外と見落とされやすい追加コストです。
特に、排水口やドレンまわりの処理は、雨水の流れを妨げないために非常に重要な工程です。場合によっては、専用の部材や加工が必要になることもあります。
既存防水層の撤去作業は、改修工事で避けられない作業になる場合があり、手間と費用がかかります。
また、撤去した防水層や廃材の処分費も、見積もりに含まれていないと後から別途請求されるため要注意です。
見積書でチェックすべき項目
見積書を受け取った際に確認すべきポイントは、以下の通りです。
- 単価と面積が正確に記載されているか
- 材料費と人件費が明確に分けられているか
- 使用するウレタン樹脂の種類とグレードが記載されているか
- 下地処理やトップコートの有無、層の数が明記されているか
- 工事保証の内容と期間が明示されているか
見積もりを確認することで、工事後のトラブルや追加請求を防げ、安心して契約を進められるでしょう。
ウレタン塗装防水の施工方法

ウレタン防水には複数の工法があり、建物の状態や目的に応じた選択が求められます。最適な防水方法を選ぶには、各工法の違いや特徴を知ることが重要です。
以下では、密着工法や通気緩衝工法、材料の種類について説明します。
密着工法
密着工法は、既存の下地にプライマー(下塗り材)を塗布した後、ウレタン防水材を直接塗り重ねます。比較的コストが抑えられるうえに工期も短いため、小規模なベランダやバルコニーでよく用いられています。
ただし、下地の状態が悪い場合や水分を多く含んでいると、膨れなどが起こります。欠陥を防ぐためにも、事前の下地調整が非常に重要です。密着工法は新築よりも改修時に多く使用され、予算重視の方に向いています。
通気緩衝工法
通気緩衝工法は、下地と防水層の間に通気層(通気シート)を挟みます。湿気や空気が逃げる構造にし、膨れや剥がれを防ぎます。通気緩衝工法は、特に古い建物や下地に湿気を含んでいる場合に適しています。
施工費はやや高くなりますが、長期間にわたって安定した防水性能を発揮します。防水層の膨れが多い建物の改修には、通気緩衝工法が適しています。
2液型と1液型の違い
ウレタン防水材には「1液型」と「2液型」があります。1液型はあらかじめ混合されているため、開封後すぐに使用できます。一方、2液型は主剤と硬化剤をその場で混ぜて使用するタイプで、より高い耐久性と厚みの確保が可能です。
プロの施工業者は、施工現場の条件に応じて使い分けます。耐候性や強度を求める現場では、2液型が使用されます。DIYでは扱いやすい1液型がおすすめです。
ウレタン塗装防水の施工工程

実際の施工現場では、ウレタン防水がどのような手順で仕上げられていくのでしょうか。工程を知ることで、工事の進捗管理やトラブルの予防がしやすくなります。
次に、代表的な施工の流れを3つのステップに分けて見ていきます。
下地調整からプライマー塗布
ウレタン防水の施工を始める前に、下地の調整を行います。劣化した旧防水層の除去、ひび割れや浮きの補修をします。補修後、ウレタン樹脂が密着しやすいよう、清掃をし乾燥させます。その後、プライマー(下塗り材)を塗布し、下地と防水層の密着力を高めます。
この作業を丁寧に行わないと、防水層が剥がれたり、膨れが発生します。特に、コンクリートの吸水性や油分などが問題となる場合が多く、下地の状態は常に確認が必要です。
主材(ウレタン樹脂)の塗布と重ね塗り
プライマーが乾燥した後、いよいよウレタン防水材を塗布します。
通常は2回以上の重ね塗りを行い、規定の厚み(1.5〜2mm)にします。一回目の塗布が乾燥してから二回目を塗ることで、均一で継ぎ目のない防水層が形成されます。
液状のウレタンは流動性があるため、複雑な部分にも自然に入り込み、しっかりと防水膜を作れます。塗布の厚みが不足すると防水効果が減少するため、欠陥を増やさないためにも専門業者に依頼しましょう。
トップコート仕上げと乾燥時間
ウレタン樹脂が硬化した後は、トップコート(仕上げ塗料)を塗布します。トップコートは防水層を紫外線や風雨から守り、見た目も綺麗になります。トップコートがなければウレタン層が早期に劣化してしまうため、必ず塗布しなければいけません。
乾燥時間は季節や気候により異なりますが、24〜48時間程度が目安です。完全硬化にはさらに時間がかかるため、施工後数日は立ち入りを控えましょう。
\ 簡単30秒! /
ウレタン塗装防水のメンテナンス方法

施工後のメンテナンス次第で、防水層の寿命や費用負担は大きく変わってきます。適切な管理を行えば、長期間にわたり防水機能を維持することが可能です。
ここからは、点検の時期や日常的にできる管理のポイントを解説します。
点検のタイミングと方法
点検は、施工後1年目、その後は2〜3年ごとに行うのが理想的です。専門業者による目視点検に加えて水溜まりや膨れ、ひび割れなどの劣化症状がないかチェックします。
また、排水口の詰まりやドレン周辺の浮きなども確認が必要です。小さな異常でも放置すれば雨漏りの原因になるため、異常を感じたら早めにプロに相談しましょう。
トップコート塗り替え時期の目安
トップコートは、紫外線や風雨によって少しずつ劣化します。目安としては5年ごとの塗り替えが推奨されています。怠るとウレタン層がむき出しになり、防水性能が急激に低下します。
早期に対応することでコストも抑えられ、経済的です。劣化が進む前に、定期的なトップコート再施工を行い、防水性能を長期間維持しましょう。
長持ちさせるための日常管理
防水機能を長持ちさせるために、日常的にベランダや屋上にゴミや落ち葉を溜めず、排水口を常に清潔に保ちましょう。管理を怠ると水が流れずに溜まり、浸水や劣化の原因になります。
また、重い物を引きずると防水層を傷つける恐れがあるため、取り扱いには注意が必要です。普段から防水層に負担をかけない心がけが、長寿命化に直結します。
ウレタン防水を依頼する塗装業者選び方

防水工事の成否を左右するのは、実は「どの業者に依頼するか」です。信頼できる業者を見極めることで、施工品質もアフターケアも安心につながります。
次の項目では、業者選びのポイントと確認すべき注意点を整理していきます。
信頼できる業者の見極め方
口コミや施工実績の豊富さ、対応の丁寧さなどが、信頼できる業者を見極める重要なポイントです。ホームページで施工例を公開しているか、地域密着で長年の実績があるかなども判断材料になります。
また、複数の業者に相見積もりを取ることで、対応の質も比較できます。安すぎる見積もりは注意が必要です。重要な工程が省かれていないか、必ず確認しましょう。
保証内容のチェックポイント
工事後の保証内容も、業者選びに欠かせない判断基準です。最低でも5年、可能であれば10年の保証がついている業者が理想的です。
また施工保証と材料保証が別で設定されているか、保証内容の範囲が明確かどうかも確認しておきましょう。契約時には、書面で保証書を発行し大切に保管してください。
施工不良を防ぐための対策
施工不良を未然に防ぐためには、以下のポイントを事前に確認しておくことが大切です。
- 着工前の説明が丁寧かどうか
- 工程ごとの進捗報告があるか
- 写真などで記録を残してくれるか
これらはすべて、施工の透明性と信頼性を高めるための重要な要素です。
着工前にしっかり説明してくれる業者は、顧客への配慮や技術に自信を持っている証拠です。また、工程ごとの報告や写真記録があれば、進捗を確認でき、トラブル防止にもつながります。
また、工期を守るだけでなく天候による延期のリスクも事前に共有してくれる業者を選ぶと安心です。
ウレタン塗装で防水をし外壁を守ろう

ウレタン塗装防水は、柔軟性や密着性に優れ、複雑な形状にも対応できる防水工法です。その反面、施工には高度な技術が求められます。施工者の経験値や環境管理によって仕上がりに差がでてしまうので、業者選びは慎重に行いましょう。費用面では、相場の把握と見積書のチェックが不可欠です。
また、施工後の定期的な点検とメンテナンスで、長期間建物の防水性能を維持できます。
ウレタン塗装防水を成功させるためには正しい知識と判断力、適切なメンテナンス計画が不可欠です。本記事を参考に、ウレタン防水を取り入れてみてください。
ウレタン防水塗料を使用した外壁塗装を検討されている方は、ぜひペイプロをご利用ください。ペイプロは、外壁塗装の専門業者を比較・紹介してくれる無料のマッチングサービスです。厳選された優良な外壁塗装業者を紹介しているため、ウレタン防水塗料に対応している業者も揃っています。ご相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください!